top of page
検索
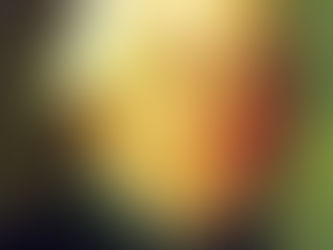

1月17日 誕生日 フランソワ=ジョゼフ・ゴセック
1月17日 誕生日 フランソワ=ジョゼフ・ゴセック(François-Joseph Gossec,1734.1.17〜1829.2.16) バロック後期からロマン派初期まで、フランスで活躍したベルギー出身の作曲家・指揮者。 95歳まで生き、42曲以上の交響曲、20作以上の劇場用作品、多数の宗教曲、室内楽曲を残した。有名な「ガヴォット」は歌劇『ロジーヌ』から旋律を取って作られた。
1月17日


1月16日 命日 レオ・ドリーブ
1月16日 命日 レオ・ドリーブ(Clément Philibert Léo Delibes, 1836.2.21〜1891.1.16) フランス・ロマン派音楽の作曲家。バレエ音楽『コッペリア』『シルヴィア』やオペラ『ラクメ』などで知られ、「フランス・バレエ音楽の父」と呼ばれる。 音楽家の多い家系で、家族の後押しでパリ音楽院で音楽を学ぶ。「ジゼル」の作曲家・アダンに二年間師事。卒業後は稽古ピアニストからパリ・オペラ座の副合唱指揮者の職を得て、劇場のバレエ作曲家の道を歩んでいく。 オペレッタやオペラも数多く書いたが、特に英植民地時代のインドが舞台の『ラクメ』は、オペラ・コミック座で1,500回以上上演された。 音音工房のドリーブ 「花の二重唱」今野沙知恵/藤井麻美 https://youtu.be/PxxAJ6tAorc
1月16日


1月15日 誕生日 西條 八十
1月15日 誕生日 西條 八十(さいじょう やそ、1892.1.15〜1970.8.12) 東京出身の詩人、作詞家、仏文学者。英国人女性に英語を学び、早稲田大英文科卒。詩集『砂金』で象徴詩人としてデビュー。鈴木三重吉による雑誌『赤い鳥』にも加わり「かなりあ」などの童謡を発表。2年間フランスのソルボンヌ大学に留学した後、早稲田大学教授に就任。歌謡曲の作詞では「東京行進曲」「青い山脈」「蘇州夜曲」など多数のヒット曲を残した。研究者として『アルチュール・ランボオ研究』もある。「苦」に通じる「九」を抜いた「八」と「十」を用いて命名 音音工房の西條八十 「お菓子と娘」金子美香/朴令鈴 https://youtu.be/ZkZDboFrIuQ
1月15日
1月14日 誕生日 三島 由紀夫
1月14日 誕生日 三島 由紀夫(みしま ゆきお、1925.1.14~1970.11.25) 東京出身の小説家、劇作家、評論家。本日生誕100年。戦後日本の文学を代表し、ノーベル文学賞候補にも。 その生涯や作品については多く語られているので、日本オペラの原作となった作品を紹介する。 あやめ(牧野由多可) 金閣寺(黛敏郎) 黒蜥蜴(青島広志) 午後の曳舟(ヘンツェ) サド侯爵夫人(青島広志) 浄土(ジェームズ・ウッド) 卒塔婆小町(石桁真礼生) 班女(細川俊夫) 鹿鳴館(池辺晋一郎)
1月14日


1月13日 命日 スティーブン・コリンズ・フォスター
1月13日 命日 スティーブン・コリンズ・フォスター(Stephen Collins Foster、1826.7.4~1864.1.13) 19世紀半ばのアメリカ合衆国を代表する歌曲作曲家。 事業家の裕福な家に生まれ、子供の頃から様々な楽器に親しんだが、後に父親が事業に失敗し、学校を転々とする生活を送る事になる。転校先で「ミンストレルショー」(白人が黒人の格好で演じる芝居)に出会い、仲間と劇団を作りショーを行い評判となった。後年、「フォスターのミンストレル・ソング集」が出版される契機となった。1850年に結婚し娘が生まれる中、次々とヒット曲を生み出していく。「ケンタッキーの我が家」「スワニー河」「金髪のジェニー」 しかし再び大きく事業を展開していた両親と兄が立て続けに亡くなり、借金暮らしに陥る。また時代が奴隷制批判に傾き収入は激減、酒に溺れる生活の中、胸を病み37歳で亡くなった。 前述以外にも「草競馬」「おおスザンナ」など、フォスターの歌は日本をはじめ世界中で愛唱されている。
1月13日


1月12日 命日🙏 別宮 貞雄
1月12日 命日🙏 別宮 貞雄(べっく さだお、1922.5.24~2012.1.12) 東京都出身の作曲家。 東京大学理学部物理学科を卒業した年に「管弦楽のための二章」を発表して作曲家としてデビュー。翌年から同大学文学部美学科で学び直し1950年卒業。1951年フランスに渡り、パリ国立高等音楽院でミヨー、メシアンらに師事。因みにミヨーのクラスを受験した際、別宮が合格したためシュトックハウゼンは不合格となった。帰国後は桐朋学園、中央大学で教授を務めた。 歌曲「さくら横ちょう」が大変有名だが、交響曲、協奏曲、室内楽曲も数多く書いている。オペラには「有馬皇子」など 音音工房の別宮貞雄 さくら横ちょう」|彌勒忠史/朴令鈴 https://youtu.be/QfyeIvIbM9A
1月12日
1月11日 誕生日 大田黒 元雄
1月11日 誕生日 大田黒 元雄(おおたぐろ もとお、1893.1.11〜1979.1.23) 東京都出身、日本の音楽評論の草分け的存在。父・重五郎は日本の水力発電の先駆者で、芝浦製作所(現・東芝)の経営を再建し財をなした人。 東京音楽学校の外国人教師にピアノを師事し、ロンドン大学で経済学を専攻しながら、劇場に足繁く通った。フォーレの演奏も聴いたという。 この頃に集めた資料を日本に持ち帰り、現・山野楽器の店主・山野政太郎の勧めで作曲家の評伝『バッハよりシェーンベルヒ』を刊行。また、自宅にて定期的に音楽の集いを開催し、様々な作曲家を紹介。この邸宅には、プロコフィエフが日本滞在の折に、ピアノを弾きに通っていた。 戦後はNHKラジオ『音楽の泉』にレギュラー出演し人気を博した。 2,700坪に及ぶ杉並区荻窪の自邸跡地の大部分が「大田黒公園」となり、仕事場が「記念館」として保存されている。
1月11日


1月10日 誕生日 三善 晃
1月10日 誕生日 三善 晃(みよし あきら、1933.1.10〜2013.10.4)国内外で活躍した日本の作曲家。 平井康三朗に作曲とヴァイオリンを師事。東大仏文科に入学、在学中「ソナタ」が日本音楽コンクール作曲部門第1位、「ピアノと管弦楽のための協奏交響曲」が第3回尾高賞、文化庁芸術祭奨励賞を受賞し注目される。パリ音楽院に留学し帰国後東大に復学し卒業。管弦楽、室内楽、歌曲などのほか、多くの合唱曲がある。 桐朋学園大学学長、東京文化会館長など。オペラ作品には「遠い帆」 音音工房の三善晃 『五柳五酒』より五|演奏:与那城敬/朴令鈴 https://youtu.be/uLkphGiZHI4
1月10日
1月9日 誕生日 ラインハルト・カイザー
1月9日 誕生日 ラインハルト・カイザー(Reinhard Keiser, 1674.1.9〜1739.9.12) ドイツ盛期バロック音楽の作曲家。ハンブルクを拠点に活躍した。 父はオルガン奏者。幼少より音楽教育を受け、11歳からライプツィヒのトーマス学校で学ぶ。1690年代初頭からオペラ研究を重ね、ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル宮廷作曲家となる。同地およびハンブルクで歌劇が成功し、アリア、カンタータ、教会音楽など多方面で創作した。1697年以降はハンブルクのゲンゼマルクトオーパー首席作曲家として活躍。劇場が成り立たなくなると、各地を転々とし、コペンハーゲン王室礼拝堂楽長の称号を得る。晩年はハンブルク大聖堂カントルとして宗教曲に専念した。
1月9日


1月8日 命日 ポール・ヴェルレーヌ
1月8日 命日 ポール・ヴェルレーヌ(Paul Marie Verlaine, 1844.3.30~1896.1.8) 市役所に勤めながら詩を書き『艶なる宴』で詩壇デビュー。結婚していたが、アルチュール・ランボーに熱狂し、妻を捨てランボーと同棲を始める。しかし愛憎の果てにランボーを拳銃で撃ち入獄。その後も酒と男に溺れる人生を送った。 一方、彼の詩は世間に愛され尊敬され、また多くの作曲家に筆を執らせた。フォーレ、ドビュッシー、ショーソン他、数多くのフランス人作曲家が歌曲を書いた。日本でも上田敏訳「落葉」に橋本國彦、下總皖一が曲をつけている。 音音工房のヴェルレーヌ ドビュッシー『忘れられた小唄』より|盛田麻央/鳥井俊之
1月8日
bottom of page