top of page
検索


1月27日 誕生日 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
1月27日 誕生日 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart,1756.1.27〜1791.12.5) 現在のオーストリア出身の作曲家、音楽家。世界で最も有名で人気の作曲家と言える。全てのジャンルに名曲を残したが、オペラ、特にダ・ポンテ三部作においては、人間の内面世界が全て音に変換されていて、古典派の限られた和声から深いドラマが構築される事に驚きを隠せない。 モーツァルトのオペラ (初演年) アポロとヒアキントス (1767) バスティアンとバスティエンヌ (1767) 偽りの純真 (1769) ポントの王 ミトリダーテ (1770) アルバのアスカニオ (1771) スキピオの夢 (1772) ルーチョ・シッラ (1772) 偽の女庭師 (1775) 羊飼いの王 (1775) ツァイーデ(未完) イドメネオ(1780) 後宮からの誘拐(1781) カイロのガチョウ(未完) 騙された花婿(未完) 劇場支配人(1786) フィガロの結婚(1786) ドン・ジョヴァンニ(1787) コジ・ファン・トゥッ
1月27日


1月26日 誕生日 アヒム・フォン・アルニム
1月26日 誕生日 アヒム・フォン・アルニム(Achim von Arnim, 1781.1.26~1831.1.21) ドイツの詩人・文学者。ベルリンのギムナジウムへ通い、ハレ大学とゲッティンゲン大学で法律と数学を学ぶ。兄と共にヨーロッパ中を教養旅行に出かけ(1801-1804)、1806~8年にかけて友人で義兄のクレメンス・ブレンターノと共に、4巻からなる民族童話集『少年の魔法の角笛』を共同で執筆。『隠者新聞』『ベルリン夕刊紙』を発刊。詩や戯曲、論文など多くの作品を残した。 音音工房のアルニム マーラー:この世の暮らし〜『少年の魔法の角笛』より | 杉山由紀(Ms) https://youtu.be/JILWgzbDtbE マーラー:別れ 離れ https://youtu.be/dALk1VfI_Jw
1月26日


1月25日 誕生日 北原 白秋
1月25日 誕生日 北原 白秋(きたはら はくしゅう、1885.1.25~1942.11.2) 福岡県柳川市出身の詩人、童謡作家。 柳川藩御用達の海産物問屋を営む家に生まれ、1904年に上京、早稲田大学に入学。学業の傍ら詩作に励み、1909年、処女詩集「邪宗門」、2年後に詩集「思ひ出」を発表し、詩壇の第一人者となる。また1913年には初めての歌集『桐の花』を刊行、歌壇でも注目の存在となった。1919年に鈴木三重吉に誘われ、児童文学雑誌『赤い鳥』の童謡、児童詩欄を担当、1922年には山田耕筰と『詩と音楽』を刊行、今も歌い継がれる童謡が数多く生まれた。「白露時代」と呼ばれ、三木露風と並び評される近代日本を代表する詩人。 音音工房の北原白秋 「からたちの花」 馬原裕子(Sop)/朴令鈴(Pf) https://youtu.be/OtDGXP5UyMA 「この道」 小泉詠子(Ms) https://youtu.be/ANnW0Ns7kM0 「三つの小唄」 馬原裕子(Sop)/ 鳥井俊之(Pf) https://youtu.be/yd67dHlXaxE
1月25日


1月24日 誕生日 ボーマルシェ
1月24日 誕生日 ボーマルシェ(Beaumarchais) 本名ピエール=オーギュスタン・カロン(Pierre-Augustin Caron, 1732.1.24〜1799.5.18) 18世紀フランスの実業家、劇作家。『セビリアの理髪師』、『フィガロの結婚』、『罪ある母』からなる「フィガロ3部作」で有名だが、劇作家は彼の職業のひとつに過ぎず、時計職人、音楽家、司法官、実業家、貿易商、王の密使、劇作家協会設立者、出版業者と幅広く活躍。また多彩な女性遍歴を辿ったという。 彼の豪邸が立っていた通りは、現在ボーマルシェ大通りとして知られている
1月24日


1月23日 命日 サミュエル・バーバー
1月23日 命日 サミュエル・バーバー(Samuel Barber、1910.3.9~1981.1.23) アメリカの作曲家。カーティス音楽院で学びイタリアに留学。ロマン派音楽の伝統を重んじ、時に無調や12音を用いて作曲する手法をとった。ピアノの名手で、ラフマニノフの使っていたピアノを所有していた。また、「ピアノ・ソナタ」はホロヴィッツにより初演されている。 オペラにはメノッティ台本の「ヴァネッサ」、ゼッフィレッリ台本の「アントニウスとクレオパトラ」などがある。歌曲も数多く書いた。代表作『弦楽のためのアダージオ』など。 音音工房のバーバー Nuvoletta op.25/Nocturne op.13-4(佐竹由美/鳥井俊之) https://youtu.be/ZlUbfleGSNA
1月23日


1月22日 誕生日 ジョージ・ゴードン・バイロン
1月22日 誕生日 ジョージ・ゴードン・バイロン(George Gordon Byron, 1788.1.22~1824.4.19) ロマン派を代表するイングランドの詩人。10歳にして第6代バイロン男爵となる。ケンブリッジ大学で学び、卒業後、友人達と2年間地中海諸国を旅する。この体験をもとにした詩作『チャイルド・ハロルドの遍歴(Childe Harold's Pilgrimage)』の初版が、3日で売り切れるベストセラーとなる。「小説は事実よりも奇なり」の文もバイロンの『ドン・ジュアン』からの一節。社交界の寵児としてもてはやされるが怠惰な生活を送り、最後はギリシャ独立戦争に参加するも、熱病に侵され戦線に立つ事なく36歳で死去。 バイロン原作のオペラにはヴェルディ『海賊』『二人のフォスカリ』他 バイロンの詩による歌曲も多数あり、特にロシア語に翻訳されたものへの付曲が多い。ドイツ語訳にはシューマンやレーヴェ、ケルナーらが作曲。
1月22日


1月21日 誕生日 アンリ・デュパルク
1月21日 誕生日 アンリ・デュパルク(Henri Duparc, 1848.1.21〜1933.2.12) パリ生まれ。フランクの最初の弟子。サン=サーンスらと国民音楽協会を設立。37歳で神経衰弱により大部分の作品を自ら破棄。残された17曲の歌曲は、繊細な叙情表現やワーグナーの影響を受けた劇的表現に優れ、歌曲の最高傑作と謳われる。 音音工房のデュパルク 「悲しき歌」盛田麻央 https://youtu.be/Fe_9i2XLmaQ
1月21日


1月20日 誕生日 アメデ=エルネスト・ショーソン
1月20日 誕生日 アメデ=エルネスト・ショーソン(ショソン、Amédée-Ernest Chausson, 1855.1.20〜1899.6.10) フランスの作曲家。裕福なパリの家庭に生まれ、当初は法曹の道を歩むも音楽の道へ転向。ワーグナーやフランクの影響を受けつつ独自のスタイルを確立した。国民音楽協会の秘書を長く務め、自宅のサロンでは画家や文人との交流を深めた。また19世紀末のパリで対立するさまざまな音楽家同士を結びつける役割も果たした。代表作『詩曲』、『愛と海の死』、オペラには『アルテュス王』。自転車事故で44歳の若さで急逝。
1月20日
1月19日 誕生日 小倉 朗
1月19日 誕生日 小倉 朗(おぐら ろう、1916.1.19〜1990.8.26) 北九州出身の作曲家。生後3か月で東京に養子へ。音楽に囲まれた家庭で才能を磨く。早稲田、東洋音楽学校などを中退しつつも、深井史郎や池内友次郎に師事し作曲の道へ。 ドイツ古典主義派で「オグラームス」と綽名されるも、西洋一辺倒に限界を感じバルトークに傾倒し、日本民謡やわらべうたを取り入れた独自の作風を確立。オペラ「寝太」で芸術祭奨励賞を受賞し、日本語と音楽の融合を追求。戦後はNHKの放送音楽や教育にも尽力した。
1月19日

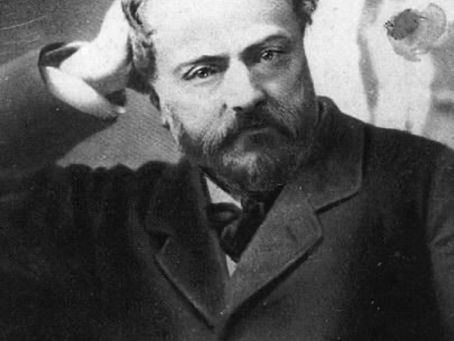
1月18日 誕生日 アレクシ=エマニュエル・シャブリエ
1月18日 誕生日 アレクシ=エマニュエル・シャブリエ(Alexis-Emmanuel Chabrier, 1841.1.18〜1894.9.13) フランスの作曲家。 幼少からピアノの才能があったが、父親の強い勧めで パリ で法律を学び内務省に就職。ミュンヘンでの『トリスタンとイゾルデ』を観劇したのを機に、39歳で公務員を辞め、音楽の道を進む。有名な『スペイン狂詩曲』の他、ピアノの小品やオペラ作品もある。
1月18日
bottom of page